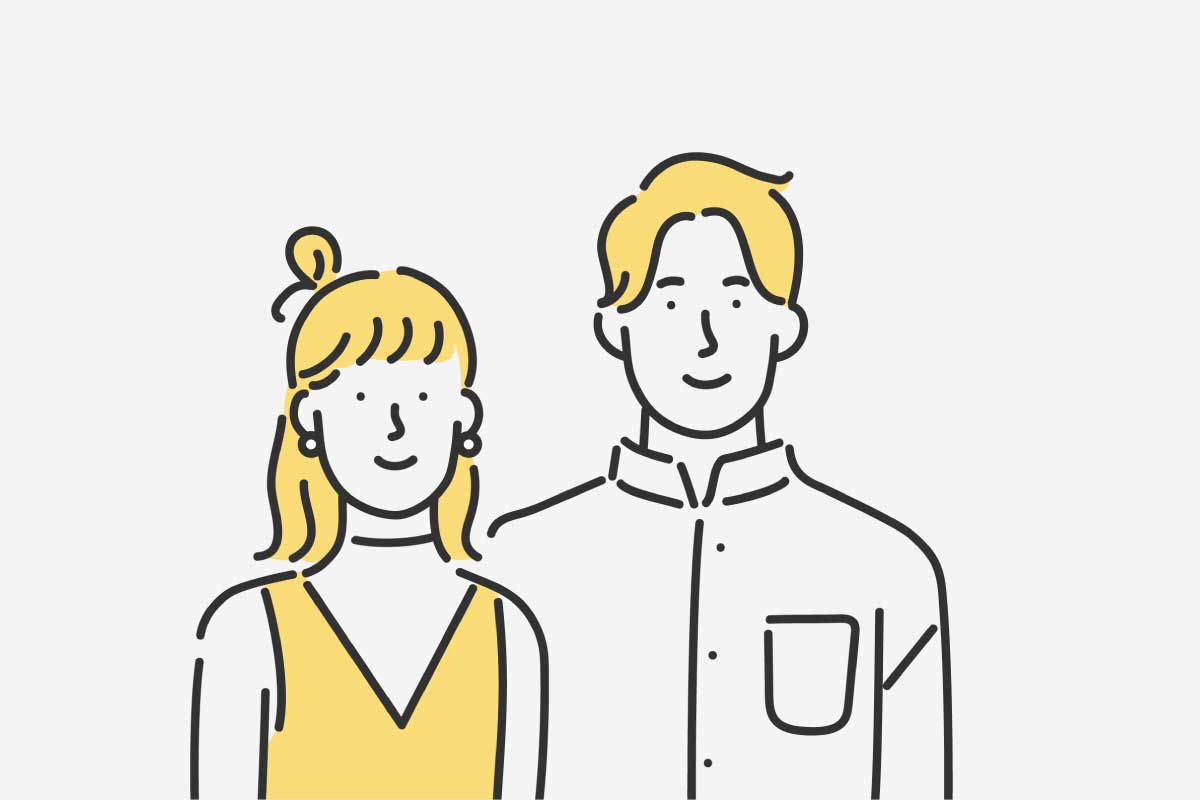売却
売却の流れ
建物の耐用年数=資産価値じゃない?査定との違いをわかりやすく解説
不動産を売却しようと考えたとき、「築年数が古いともう価値がないのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
確かに、建物には「耐用年数」という概念があり、経年劣化とともに価値が減少するとされています。
しかし実際には、耐用年数と不動産査定価格は必ずしも一致するわけではありません。
立地や管理状態によっては、築年数が経っていても高く評価されることもあるのです。
本記事では、建物の耐用年数と不動産査定の違いをわかりやすく解説し、売却時に知っておくべきポイントについて詳しくご紹介します。
建物の耐用年数とは

耐用年数の定義
耐用年数とは、税務や会計のルール上「建物が使用できる期間」として定められた年数のことです。
これは、企業や個人が不動産を保有した際に、減価償却費を計上するための基準として使われます。
建物は時間とともに老朽化し、その価値も徐々に減っていきます。
この価値の目減りを「費用」として少しずつ経費に計上できる仕組みが「減価償却」であり、そのスケジュールを決めるのが「耐用年数」なのです。
たとえば、22年の耐用年数が設定されている木造住宅を購入した場合、原則としてその建物価値は22年間で毎年等分に減少していく、という計算がされます。
ただし、これはあくまで帳簿上の話であり、「22年経ったらもう使えない」「22年経ったら価値がゼロ」という意味ではありません。
法定耐用年数の具体例(木造・RC造など)
建物の耐用年数は、その構造や用途によって異なります。
以下は代表的な例です:
[構造 耐用年数(目安) ]
木造住宅 22年
鉄骨造(軽量) 19年〜34年
RC造(鉄筋コンクリート) 47年
鉄骨鉄筋コンクリート造 50年
築20年の木造住宅であれば、税務上の建物価値はほぼ償却されている状態ですが、現実的にはまだ十分に住める家であり、資産としても価値が残っているケースが多くあります。
また近年では、リフォームやリノベーションによって、見た目や設備が新築同様になっている物件も多く、築年数だけで価値を判断するのはリスクが高いと言えます。
不動産査定における評価基準とは?

査定価格の決まり方
査定価格の決まり方 不動産の「市場価値」は、実際にその物件がいくらで売れるかを意味します。
この価値を判断するのが「不動産査定」で、専門家がさまざまな角度から評価を行います。
査定には大きく3つの方法があります。
・原価法
同じ建物を今建てるといくらか?という視点から価値を出し、そこから築年数に応じて劣化分を差し引いていく方法。
・取引事例比較法
近隣で実際に取引された類似物件と比較して、相場感をもとに価格を算出する方法。
・収益還元法
主に収益物件(アパート・マンションなど)に用いられ、家賃収入などの利回りをもとに評価する方法。
また、これらに加えて重視されるのが立地や周辺環境です。
駅からの距離、商業施設の有無、学区、将来の開発計画などは、築年数よりも強く影響するケースもあります。
建物の築年数が与える影響
築年数が進むほど、一般的には建物の評価は下がっていきます。
しかし、一定年数を超えると査定においては「建物価値より土地の価値が重視される」傾向にあります。
たとえば築30年以上の物件では、土地価格に査定が集中し、建物はおまけ程度に扱われることも。
ただし、リフォームや修繕履歴がしっかりある場合や、状態が良好で魅力的なデザインになっている物件は、例外的に高い評価を得ることもあります。
築年数だけで一律に価値が決まるわけではないのです。
「耐用年数」と「査定価格」の違い
この2つの違いは、不動産を売却・保有するうえで非常に重要です。
・耐用年数
あくまで帳簿上の“会計ルール”。
減価償却を終えたら、税務上の建物価値はゼロになります。
・査定価格
現実の“市場価値”。実際に売買されるときの価格は、建物の状態や立地、周辺需要に大きく左右されます。
たとえば、築30年の木造住宅でも人気のエリアにある、デザインリノベーション済みの物件であれば、高値で取引されるケースもあります。
つまり、会計上の価値がなくなっても、実際の不動産価値が消えるわけではないのです。
耐用年数が過ぎた建物の取り扱い

売却時に知っておきたいこと
「築年数が古い物件だから、どうせ売れないだろう…」
そんなふうに諦めてしまっている方は、実は大きなチャンスを逃しているかもしれません。
築年数が経過した建物でも、その活かし方次第で価値を再発見できることがあります。
以下は代表的な3つの活用パターンです。
① 建物付きでそのまま販売
近年は、“古さ”を味として楽しむスタイルが人気です。
特に古民家風の建物や、レトロ感のあるヴィンテージ住宅は、若年層やアート・自然志向の層から注目を集めています。
「手を入れながら住みたい」「味のある家に住みたい」というニーズに応えることで、古さが「売り」に変わることも。
② 更地にして土地だけで販売
一方で、建物が大きく傷んでいたり、建築条件付きで買いたいという声が多い地域では、更地にして販売するほうが効果的なケースもあります。
特に都市部では、「土地として購入し、建て直す」という前提の購入者も多く、建物があることで逆に評価が下がることも。
解体費用はかかりますが、トータルで見れば早期売却に繋がる可能性があります。
③ リフォームやリノベーション後に販売
「築年数がネックだけど、場所や間取りは良い」――
そんな物件には、部分リフォームやフルリノベーションが効果的。
最近では、「リノベ済み中古住宅」という形で、新築にはない個性を求める買主が増えています。
あらかじめリフォームしておくことで、内見時の印象が良くなり、即決につながることも。
減価償却が終わった後の税務処理
建物は耐用年数を過ぎると、減価償却費を計上することができなくなり、帳簿上の建物価値はゼロになります。
ですが、ここで注意したいのが、「帳簿価値がゼロ = 資産価値がゼロ」ではないという点です。
減価償却が終了していても
・固定資産税評価額として一定の価値が付けられている
・売却時の譲渡所得の計算において「取得費」として建物部分が必要になる
このように、税務上も建物の存在は無視できません。
さらに、減価償却後も賃貸に出せば収益を生む「収益資産」として活用できます。
帳簿価値はなくなっても、実際には住まいとしての機能も、収益性も、評価対象としての価値も残っているということを、ぜひ覚えておいてください。
不動産価値を高めるためのポイント
築年数が進んでも、「きちんと手入れされている物件」は査定でも好印象を与えます。
それは、買い手や借り手にとって「安心できる住まい」の証になるからです。
以下のポイントを意識することで、物件価値を上手に保ち、引き上げていくことが可能です。
■ 定期的なメンテナンスを欠かさない
屋根・外壁・配管・防水などの経年劣化しやすい箇所は、定期的な点検と修繕が不可欠です。
後回しにすると修繕費が膨らみ、買い手から「手入れされていない」と見なされてしまうことも。
■ リフォームや修繕の履歴を記録しておく
「いつ・どこを・どんな内容で直したか」を記録しておくことで、査定時や内見時に大きな信頼感を生みます。
場合によっては、リフォーム内容がプラス評価として査定価格に反映されることも。
■ エリアの再開発・街の変化に目を向ける
周辺エリアの再開発計画や商業施設の新設、交通インフラの整備といった情報は、物件の価値に直結する外的要素です。
タイミングによっては「今売れば高く売れる」こともあるため、地域情報を日頃からチェックしておくと良いでしょう。
こうした小さな工夫が、いざというときに「他と差がつく武器」となります。
古さではなく、“手のかけ方”が未来の資産価値をつくるのです。
まとめ
不動産の価値を考えるうえで、「耐用年数」と「査定価格」はまったく別物です。
耐用年数は税務・会計上のルールにすぎず、それが過ぎたからといって、建物の価値がゼロになるわけではありません。
実際の査定では、立地や状態、リフォーム履歴などが加味され、市場価値としての価格が決まります。
築年数が古くても、管理の仕方や見せ方次第で物件の価値は十分に保てるのです。
近年は、リノベ済み中古住宅や古民家のような“個性ある物件”が注目され、購入希望者も増えています。
「もう古いから」と諦める前に、物件の魅力や活用方法をもう一度見直してみましょう。
最新の記事